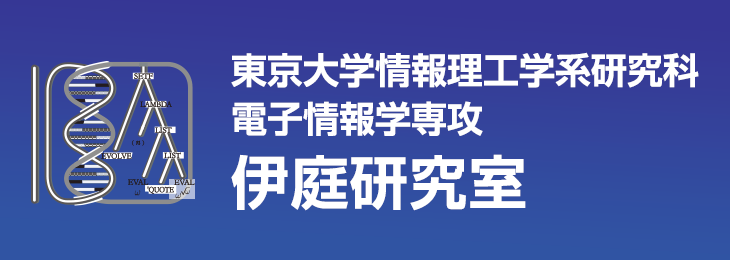シミュレーション学
担当教官
伊庭 斉志(いば ひとし) 教授
講義のやり方
本講義は原則対面である。
ただしzoomでの配信も併用する。リンク情報は以下の通りである。
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/82377182156?pwd=yLB1CPq1ZRDDEAbpUvcSfk5RxPChJb.1
ミーティングID: 823 7718 2156
パスコード: 450559
講義内容
「シミュレーション学」では、大学院学生を対象に、
- 計算機上のシミュレーションの基本概念、
- 進化論的計算手法の基礎、
- マルチエージェント計算、
- 事象駆動型シミュレーション、
- 人工生命に基づくシミュレーション技法
などについて、 勉強してもらう。これらはいずれも、 コンピュータをシミュレーションの道具として使用しようと と思っている学生はもちろん、人工知能や他の分野の勉強をする学生にとっても 必要不可欠となる基礎事項である。
教科書として、 複雑系のシミュレーション:Swarmによるマルチ・エージェ ントシステム"(伊庭斉志著、コロナ社) を指定する。
さらに、英語版としては
- Iba,H., "Agent-Based Modeling and Simulation with Swarm" (Hitoshi Iba, CRC Press, Studies in Informatics Series)
- Iba,H., "AI and Swarm: Evolutionary approach to emergent intelligence", ISBN-10: 0367136317, CRC Press, 2019.
がある。 講義に関する補足説明や講義レポートの作成に必要な情報は すべてこの教科書に書かれている。
また参考書としては 「人工知能の創発(オーム社)」がある。
講義では複雑系と人工生命のシミュレーションツールであるSwarmを 用いる。 Swarmシステムのホームページは、 Swarm であり、必要なシステム、マニュアル、付属資料はここから ダウンロードできる。 授業中でインストールの仕方、使用方法、実際的な シミュレーション技法などの概略は説明するが、 その詳細は 教科書を参照してほしい。 教科書との違い(インストール方法の最新版)は ここにある。
評価は出席調査(講義当日に出題する小課題・アンケート回答)とレポートで行う。 自分で複雑系のシミュレーションプログラムを 作成などしてレポートを提出してもらう。 もっとも大切なのは自分で考えて、自分でプログラムを 作り上げることである。いかに自分で創意工夫したかがひしひしと伝わってくるような レポートであることが望ましい。